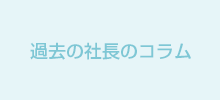社長のコラム
『測量の日』
今日、6月3日は『測量の日』です。昭和24年6月3日に測量法が公布されたことからこの日を『測量の日』として定めています。その背景には、現代社会において、測量や地図の大切さが一般の人には分かりにくくなってきたことから、その重要性を少しでも多くの人に理解してもらうことを目的に定められています。
古今、人類が生活していく上で「測量」が不可欠な技術であることは言うまでもありません。地球上で人類が生活するためのもの造りを行う上で、位置と形状を決めるのに、最初に必要となるのが「測量」です。約5000年前には古代エジプトで高度な天文観測と距離測量、水準器等により、巨大なピラミッドを築造したことが伝えられています。日本での測量は、7世紀初頭の聖徳太子の時代に、当時の隋から測量技術を持ち帰り、全国の田の大きさを測量したことが始まりのようです。その後、今から200余年前に、伊能忠敬が天文観測と歩測や検縄等による地道な距離計測で正確な日本地図を作ったことは、測量が地図という形・成果となったことから、多くの人に知られているのではないでしょうか。
近年、測量技術は急速に進歩しました。私が測量と出会ったのは、今から40年ほど前です。その頃の測量は、距離計測は鋼製巻尺、平面測量はアリダートを用いた平板測量が主流で、たいへん地道な作業でありました。計算も電卓による手計算、作図はトレーサーによる根気を要するものであったと記憶しています。
今私たちが用いているトータルステーションやGNSS測量、レーザー計測やCAD等により、正確で速い仕事が出来ることなど、当時の私には想像すらできませんでした。
今日の『測量の日』に、私たちの関わる測量をはじめとする、土木設計、地質調査の進歩や未来に思いをはせること(夢)。先達が築いてきた技術や考え方を知り、それを大切にしつつ、常に新しい技術を取り入れチャレンジすることにより成長し続けていくこと(伝統と革新)をする機会とします。
和田晶夫