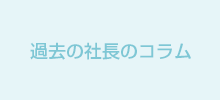社長のコラム
2008年6月02日
『測量の日』
6月3日は「測量の日」です。
「測量」は基礎的分野であり、市民生活には直接的な関わりが薄いことから、その存在は目立たず、あまり認識されていません。そのようなことから、「測量の日」は多くの人に測量の意義、重要性に対する理解と関心を高めてもらうことを目的として国土交通省が主唱して平成元年に定められました。
何故、6月3日が「測量の日」なのかというと、「測量法」が制定されたのが昭和24年6月3日ということからのようであります。
「測量」という言葉は中国の「測量天地」という言葉から由来しているようで、測量技術の原点は天文観測と土地丈量であることを示しています。
現在では光波測距儀の普及や、人工衛星を利用したGPS測量などの最先端の技術の活用により、効率的で高精度の測量が行われています。日本での本格的な測量は1800年に伊能忠敬が蝦夷地で行ったのが始めてであると言われ、羅針盤、間縄等による土地測量と天文観測を組み合わせ、高精度の日本地図を作成しています。
当時の記録や文献がドキュメント番組で紹介されるのを見るたびにその先人の技術に対する情熱に感動いたします。
当社が行っている全ての業務の原点は「測量」であります。
この「測量の日」にそれぞれが自分たちの業務の意義、意味について考え、向上心、責任、使命感の高揚につながれば私たちにとっても良い日となるのではないかと思います。